お許しをいただきまして、区長並びに関係部長に、さきの通告に従い、自由民主党議員団を代表して一般質問をさせていただきます。
初めての一般質問ですので、大変緊張しております。途中で声などかけられますと、思わずそちらに気をとられてしまい、ただでさえ初めてでお聞き苦しいところを、より聞き苦しくなってしまいますので、ご清聴のほどよろしくお願い致します。(「わかった」との声あり)
質問に先立ちまして、青木区長の所信表明の中で語られた、子どもが楽しく学べるふるさとづくりを初めとする6つのふるさとづくりを重要施策、重点事業に、子供たちが未来に夢と希望を持って成長し、自分が生まれ育った街を、誇りあるふるさととしていつまでも自慢できる、そんなふるさとと呼べる葛飾の実現に向けて、微力ではありますが協力をさせていただきます。
また、福祉総合窓口の整備、コールセンターの開設、すぐやる担当課の新設など、区役所改革に向けての新たな取り組みは、大いに評価するところでございます。今後も、区民の目線に立った業務改善を進めていただきたいと思います。
それでは、質問に入らせていただきます。
まずは、区長の所信表明の中で触れられた女性特有のがん検診推進事業のうちの子宮頸がん予防についてと木造住宅の耐震改修助成制度の2項目について、次に、亀有駅北口の街づくりについて、そして教育関係で、小中学校における土曜日授業の実施についてと、学力調査についての2項目、計5項目についてお尋ねします。
近年、世界的には、子宮頸がんは予防できるがんという認識が定着してきました。それは、子宮頸がんの発症にはヒトパピローマウイルスHPVの感染が大きくかかわっていることが判明し、発生原因が解明されてきたためです。
また、成人女性の80%が一度は発がん性HPVに感染していますが、ほとんど一時感染で、約2年間のうちに自然抗体により消滅します。ですが、ごく一部で自然治癒されず、ウイルスの感染が長期間続くと、数年から数十年かけて、がん化していくと考えられています。
世界では2分間に1人、日本では1日約7人の女性が子宮頸がんで命を落としています。特に最近は、妊娠・出産年代の20歳代、30歳代の罹患率が増加傾向にあり、これは少子化問題の面から見ても社会的に重大な問題であり、早急な取り組みが必要です。
本区では、平成22年度におきましては、今年度に引き続き、無料クーポン券や受診票とともに、検診手帳の交付、保存版リーフレットを配布するなど、がん検診を受診できる環境をつくろうとする、その積極的な取り組みは大いに評価するところでございます。
島根県では、公費での子宮頸がん検診を見直しました。子宮頸がんはHPVに感染してからがん化するまで5年以上かかる特徴があるため、地域検診に細胞診とHPV検査の併用を導入し、両検査で陰性なら受診間隔を3年、HPV検査陽性・細胞診陰性なら毎年受診、細胞診疑陽性・HPV検査陰性以上は医療機関受診と判断して、経費削減に成功したそうです。
また、咋年の12月末には、10歳以上の女性を対象にした子宮頸がん予防ワクチンが発売されました。現在の予防ワクチンは100%のHPVに有効というわけではありませんが、子宮頸がんの一時予防であるHPVワクチンを接種することで、多くのかけがえのない命が守られると考えられます。
そこで、質問させていただきます。
まず第1に、日本のがん検診受診率は、OECD経済協力開発機構加盟国30カ国の中でも最低レベルと言われています。本区における子宮頸がん検診の受診状況をお聞かせいただきたい。
第2に、島根県の子宮頸がん検診では、通常の細胞診に加え、子宮頸がんの原因であるウイルスを調べるHPV検査を実施し、受診率と費用対効果を向上させています。ウイルスがなければ、がん検診の受診間隔を長くすることが可能になるというモデル事業ですが、必要のない検診を減らすことで、結果的に検診の公費負担も減らせると考えます。今後、本区でもこのような取り組みをするべきだと考えますが、いかがですか。
第3に、昨年の12月に日本でも子宮頸がんワクチンが発売されました。接種費用は大変高額と聞いていますが、現在の本区での接種状況及び接種金額を教えていただきたい。
第4に、HPVワクチンを接種することで、子宮頸がん検診の受診率が低い若年層の子宮頸がん発症を大幅に減少できると考えますが、今後の公費負担接種についての考えをお聞かせください。
また、既に公費負担接種を行っている自治体があると聞きましたが、他の自治体の状況を教えていただきたい。
続いて、木造住宅の耐震改修助成制度についてお伺いします。
葛飾区では、平成21年度から新たに耐震改修のための設計費助成、20万円限度を始められ、また、耐震改修費の助成につきましても、50万円限度から80万円限度に増額するなど、区内の木造建築物の耐震化の促進に対する取り組みは評価させていただくところです。
近年、大規模な地震が相次ぎ、東京においても、いつ地震が起きてもおかしくない状況にございます。
このような状況にあって、葛飾区内には、木造密集地域内を初め、旧耐震と言われる昭和56年以前の旧建築基準法により建築された住宅などの建築物が多く残っています。
平成7年の阪神淡路の大震災でも、この旧耐震基準の建築物の多くが被害を受けていることから、旧耐震基準で建築された建築物に対する安全性の確保が喫緊の課題であり、区民の生命や財産を守るために、既存の建築物の耐震化を積極的に進めていく必要があります。
また、費用の点から、耐震改修をしたくてもできないといった高齢者などの災害弱者の命を守ることも大変重要であり、耐震シェルターの設置についても積極的な支援が必要だと考えています。
また、災害弱者の保護のために、墨田区、渋谷区では、1部屋だけでも補強して命だけは守るための空間を確保するという簡易補強制度の取り組みをしていると伺っています。
そこで、質問させていただきます。
まず第1に、木造住宅の耐震化を積極的に進めるべきだと考えますが、耐震化の助成制度の実績が低い状況が続いています。このことについて区はどのように評価しているのですか。
第2に、高齢者などの災害弱者の安全を確保することも大変重要であると考えていますが、耐震シェルターの設置への助成制度の実績も低い現況について、区はどのように評価しているのか、あわせてお聞かせください。
第3に、本区での耐震シェルターと同様の考えでありますが、命だけは守るための空間を確保するという墨田区、渋谷区での簡易補強制度の取り組みについて、どのように評価しているのかお聞かせください。
第4に、このような状況を踏まえ、耐震化などを促進するために、区として今後どのように取り組むべきだとお考えですか。
次に、亀有駅北口のまちづくりについて質問いたします。
亀有駅周辺の街づくりにつきましては、平成8年に、亀有駅南口地区第一種市街地再開発事業が完了し、その後、平成18年には、日本板紙跡地に大規模マンションや大型商業施設などがオープンするなど、南口を中心として街づくりが大きく進展してきました。
一方、北口につきましては、小規模ながら古くから駅前広場が整備されており、霞ヶ関や大手町といった都心の官庁街、ビジネス街に直結する玄関口として、かつては隣接する自治体からも人の集まるにぎわいのある街でしたが、つくばエクスプレスの開通など、さまざまな社会状況の変化などから、駅前ロータリーに面した好条件の土地にさえも、空き店舗や空き家が多くなっています。
現在、亀有駅周辺では、こちら葛飾区亀有公園前派出所の両さん像を活用した買い物客の回遊性の確保や、両さんのラッピングバスの運行など、商業関係者を中心としたソフト的な街づくりが進められておりますが、北口の方々からは、北口の再開発など、ハード的な街づくりを望む声も多く耳にします。
駅前広場が既に整備されていることなど、基盤整備の必要性などから、行政が主体となり街づくりを進めることは難しい面が多いとも考えますが、地域の方々の声を街づくりに生かすことができればと考えているところでございます。
そこで、質問させていただきます。
まず第1に、区として、現状の亀有駅北口周辺の状況をどのように認識しているのですか、お伺いいたします。
第2に、亀有駅北口において、地域の方々の意見を尊重した街づくりを実現させるために、区としてどんな支援が可能であるのか、お聞かせください。
次に、小・中学校における土曜日の授業の実施について質問いたします。
まず、本区、小中学校における学力向上のための授業時数の確保策としての土曜日授業についてお伺いいたします。
葛飾区では、平成15年から、葛飾区教育振興ビジョンに基づくさまざまな施策を進めてこられました。全国に先駆けて実施した夏季休業日の短縮による授業時数の確保、学習支援講師の派遣による習熟度別授業の実施、科学教育センターによる理科支援、確かな学力の定着度調査に基づく授業改善プランの作成など、学力向上のために、本区が積極的な取り組みを実施されていることについては、大いに評価いたしたいと思います。
また、平成22年11月には、こうした成果や課題を踏まえて、葛飾区教育振興ビジョン第2次を策定し、およそ60年ぶりの教育基本法の改正や、これを受けて改正された学校教育法、さらには、これに基づき改訂された新しい学習指導要領に対応するため、本区では、さらにこうした施策の充実、発展に取り組まれているものと思います。
次代を担う、かけがえのない子供たちには、現代社会を生き抜くために必要な基礎的、基本的な知識、技能や思考力、判断力、表現力などの育成につながる教育が何よりも重要であります。これまでの葛飾区教育振興ビジョンに引き続き、新たな葛飾区教育振興ビジョン第2次で示された取り組みを着実に推進し、葛飾区の教育をさらに前進させることを強く望むものであります。
さて、本区では、先ほどお話をしたとおり、学力の定着、伸長を目的とした授業時数を確保するため、全国に先駆けて夏季休業期間の短縮を実施しました。
一方、国は、こうした本区の取り組みを後追いするかのように、新学習指導要領の中で、小学校は平成23年度、中学校は平成24年度に、授業時数の増加を定めたと聞いております。学力の定着のために授業時数を確保する動きは、まさに葛飾区が先鞭をつけたと言えるのではないかと思います。しかし、その本区においても、今後はさらなる授業時数の確保が求められております。
このたび東京都は、学習指導要領の改訂を機に、土曜日における学校授業の実施を可能とする通知を各区市町村教育委員会に発送いたしました。学校週5日制の下での土曜日の活用についてと題するこの通知では、学校週5日制の趣旨を生かして土曜日の活用を行うようにという前提条件がついていますが、これは事実上、土曜授業を積極的に実施するようにと、東京都が区市町村に指示をしている通知であると思います。これを受けて、本区では、試行として、平成22年度から土曜日を活用した授業を実施する方向であると伺っております。
そこで、幾つか土曜授業の実施に関して質問をさせていただきます。
まず第1に、本区では、平成22年度は試行期間ということですが、東京都からの通知を踏まえ、区として今回の土曜日授業を実施する目的についてどのように考えているのか、お聞かせください。
第2に、土曜授業の実施日数についてであります。
東京都教育委員会からの通知では、実施内容について、土曜日における教育課程に位置づけられた授業の実施は、各月2回を上限とすると記述されております。これに対して、本区では、土曜日授業の実施については年間10回を上限とし、少なくとも年5回は試行することとされたようであります。
本区の子供たちの学力は、葛飾区教育振興ビジョンに基づくさまざまな取り組みにより、上向きの傾向にあるとはいえ、都の学力調査などでは、23区内で依然として厳しい状況にある中で、上限を10回と定める必要があるのか、疑問であります。学校の状況によっては、東京都教育委員会の通知のとおり、月2回の実施も可能ではないかと考えます。
そこで、より積極的に土曜日の授業を確保すべきと思うのですが、いかがでしょうか。
第3に、土曜授業の円滑な実施についてであります。
学校週5日制の下での土曜日授業でありますので、教員の負担が過重にならないようにする配慮も必要であり、また、保護者や地域にも、学校が土曜日の授業を行うことに対する理解や協力が必要になってくるものと思います。
東京都教育委員会からの通知の中にも、校内の指導体制の確立と保護者、地域住民の十分な理解を得ることが求められていましたが、何よりも、この土曜授業の目的、必要性、制度の内容などについて、すべての関係者に対する周知が必要であると考えます。
そこで、教育委員会としては、こうした関係者への周知、理解をどのように進めようとしているのか、お伺いいたします。
最後に、学力調査についてお伺いいたします。
国が実施している全国学力・学習状況調査については、昨年12月に、調査対象校を悉皆方式から抽出方式に変更する方針が表明され、さらには、政府の行政刷新会議が、これを事業仕分けの対象とするなど、調査対象校が32%に縮小されました。このため、全体を対象としていないことから統計の精度が低くなり、都道府県や自治体間の学力比較が正確にはできなくなりました。
また、悉皆の調査であれば、3年前に小学6年生だった児童が、ことし中学3年生として全国学力・学習状況調査に参加することで、初めて3年間の学習の成果を検証できる機会であるにもかかわらず、今回の学力調査に多くの子供たちが参加できないという不合理が生まれることになりました。国の事業費削減のためとはいえ、残念なことであると思います。
さらに、抽出率については、全体としては、32%ですが、小学校25%、中学校44%と異なり、また、都道府県別では、高知県は57.6%であるのに対して、東京都は17.3%と大きな差がつくなど、ばらつきがあります。さらに、抽出対象以外の学校も、希望すれば問題の提供を受けられるとされたことで、学力調査の実施状況は、各自治体でさまざまになると思われます。
そこで、お尋ねいたします。
本区では、こうした国の学力テストの変更の動きに対して、どのようにお考えでしょうか。また、区としては、全国学力テストヘの参加にどのような方針で対応したのでしょうか。お聞かせいただきたいと思います。
続いて、本区が国や東京都とは別に、独自に実施している確かな学力の定着度調査について伺いたいと思います。
本区では、小学校4年生から中学校3年生まで、全校悉皆による調査を、平成17年度よりこれまで5年間継続して実施しております。
これらの調査は、毎年継続することで、児童・生徒一人一人の学力の定着状況について経年変化がとらえられることができます。もともと本区の学力調査の目的は、他との比較ではなく、個々の児童・生徒の基礎、基本の学力の到達状況を踏まえ、よりきめ細やかな個人への指導を行うために行っているものであると伺っております。私は、こうしたことから、基礎的自治体としての葛飾区が独自に学力調査を行うことは、非常に大きな意味を持っていると考えています。
本区が、児童・生徒の学力向上に向けて取り組まれる、さまざまな施策の重要な基礎資料にもなるものでありますので、今後とも、確かな学力の定着度調査を継続されることを期待しております。
さて、そこで質問をさせていただきます。
学力調査は、調査実施後の分析から、教師の授業改善につなげ、児童・生徒の学力向上を図ることが大切であると考えます。各学校では、この調査に基づき授業改善プランを作成して、より充実した授業への改善に取り組んでいると聞いておりますが、この改善プランとはどのようなものなのでしょうか。具体的な実効性の上がるプランでなければならないと思います。いかがでしょうか。
次に、学力調査の問題作成についてお伺いします。
私は、学力は積み重ねが重要であると考えております。特に算数、数学といった教科では、途中でつまずくと、次の応用の段階に進めず、教科に興味が持てなくなったり、勉強自体が嫌いになったりしてしまいます。学力向上のためには、そのつまずきの箇所をつくらないこと、もしくは、できるだけ早く、そのつまずきを乗り越えさせることが必要であります。区の学力定着度調査によって、そのつまずきの箇所を把握できれば、全体としての学力の向上につながると考えます。
そこで、例えば、中学2年のテストの場合には、中学2年生の問題を出題するだけでなく、それ以前の学年の問題も織りまぜ、どこでつまずいたかがわかるような問題を出題するべきではないかと思っております。
そこで、お尋ねいたします。
本区の学力調査は、学習到達度調査と学習意識調査の双方を関連させ、児童・生徒の学習状況の全体像を把握している点に特徴がありますが、その基本である学習到達について、児童・生徒のつまずき箇所を把握できるように問題を作成しているのか。また、具体的にどのような配慮、工夫をされているのか、お伺いいたしたいと思います。
以上で、私の一般質問を終わらせていただきます。区長並びに関係部長におかれましては、1年生議員の私にも十分理解ができますよう、具体的なお答えをお願い致します。また、各議員の皆様におかれましては、当初のお願いのとおりご清聴いただき、心より感謝いたします。ありがとうございました。(拍手)
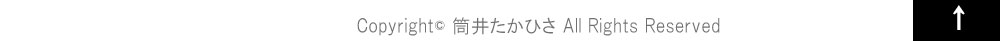
|

